●TDA1387 LR分離 4パラ用LCD基板 組み立て方
まだ送付は行っておりませんが、組み立て方を公開します。
そろそろ基板が上がってきてもいいのですが、、、
★くみたて方法
基本的に、基板のシルクに書かれた通りに、部品を実装していく。
ただし、100Ω部分は、220Ωもしくは、200Ωが添付されているのでそれを付ける。
ここはLCDバックライトの電流制限で、200〜470位でいいような気がする。
さらにSDAプルダウンに2,2Kを実装。
あとは写真を参考に部品をつけていく。
まずは裏
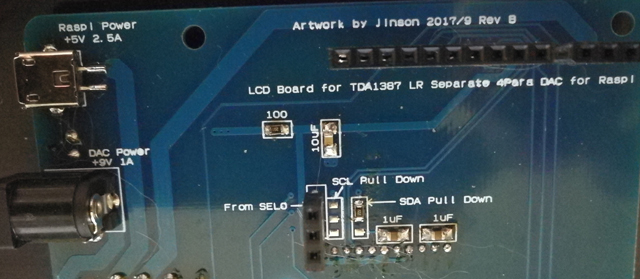
DAC PowerのACアダプタ用コネクタと、From SEL0のコネクタは、基板から突き出ないように、足を整えること。見ればわかるけど、液晶と干渉する。基板と面一になるようにする。
From SEL0と、DACへの給電コネクタは、ともに3ピン ピンソケットとなっている。
添付部品で、8ピンのピンヘッダがあるが、それを切って、3ピンを2個つくって使うこと。
そろそろ基板が上がってきてもいいのですが、、、
★くみたて方法
基本的に、基板のシルクに書かれた通りに、部品を実装していく。
ただし、100Ω部分は、220Ωもしくは、200Ωが添付されているのでそれを付ける。
ここはLCDバックライトの電流制限で、200〜470位でいいような気がする。
さらにSDAプルダウンに2,2Kを実装。
あとは写真を参考に部品をつけていく。
まずは裏
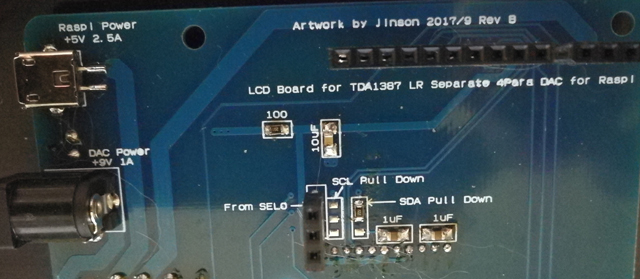
DAC PowerのACアダプタ用コネクタと、From SEL0のコネクタは、基板から突き出ないように、足を整えること。見ればわかるけど、液晶と干渉する。基板と面一になるようにする。
From SEL0と、DACへの給電コネクタは、ともに3ピン ピンソケットとなっている。
添付部品で、8ピンのピンヘッダがあるが、それを切って、3ピンを2個つくって使うこと。
ちなみに、DAC基板の上面と、LCD基板の下面までの距離は、17.5mmがベスト。
なので、コネクタは、これよりすこし短めにしておくとよい。
次は表
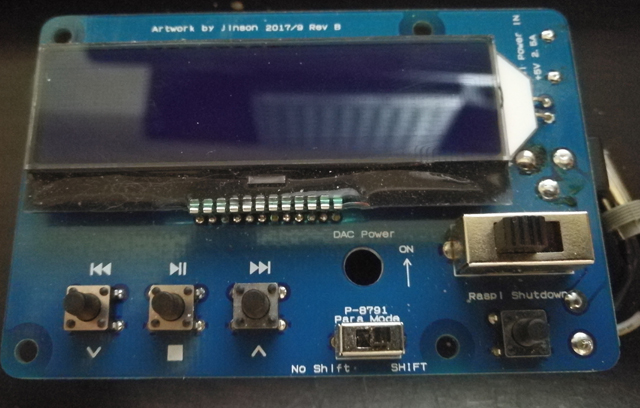
見ての通り実装していくが、液晶について注意。
まず、液晶の両面に保護フィルムが貼ってあるので、両方剥がす。
さらに、バックライトユニットは、発光側に、ツヤあり保護フィルムがはってある。これも剥がすこと。
剥がさないと、高さがましてしまい、スペーサの高さとの兼ね合いもあってよろしくない。
スペーサーだけど、これはシャットダウンスイッチとフレームがぶつかるので、逃げがつくってあるほうにあわせる。
写真とろうとおもったけど、黒くてうまく写らない。
まあ、充ててみればわかる。シャットダウンのタクトスイッチとスペーサの枠が当たるので。
あとは、DACに給電するACプラグをつければOK.
まあ、実際のところ、好きに作ればよし。
★スクリプト導入および設定
既に、ボタンや液晶スクリプトを入れている方は、単純にそれらを上書きする。
導入方法は以下の通りとなります。
Moode4の手順です。
moodeの導入手順はこちら
http://moode.local/
として、ブラウザから操作する。
・Moodeメニュー -> Configure -> System と進む。
スクロールしていくと「OPEN Web SSH terminal」というのが見つかるので、Openをクリック
ユーザ pi
パスワード moodeaudio
でログイン
volumioの場合は、
http://volumio.local/DEV/
にアクセスして、ssh を enableにする。
putty等で接続
解説はmoode向けに書いておあるが、基本おなじ。
ペーストのやり方は右クリック
ホスト名 volumio.local
ユーザ volumio
パスワード volumio
・i2cを有効にする (volumioでは不要)
以下のコマンドを投入していくが、手打ちはシンドイので、ペーストする。
ブラウザで右クリックすると「Paset from browser」というメニューが出るので、
それを選択して、以下のコマンドをペーストしていく。
sudo raspi-config
として、Interfacing Options -> I2C に進む。
これもまあ、画面見ればわかる。
カーソルキーで操作。エンターで確定
I2Cのとこで、とりあえずYESを選びまくり、最後にFINISH
・必要な物を入れる
sudo apt-get update
しばらく待つ。なにかいわれたら Yを返答
sudo apt-get install i2c-tools kakasi
これもおなじくしばらくまつ。基本的にYを返答
・スクリプトを入れる
wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_4para.bin
wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_btn.bin
さらに
mv alt_4para.bin lcd.pl
mv alt_btn.bin btn.pl
つづけて
chmod 755 lcd.pl
chmod 755 btn.pl
・自動起動に登録
sudo nano /etc/rc.local
一番最後の行に
exit 0
があるので、その上に以下を追加
/home/pi/lcd.pl & > /dev/null 2>&1
/home/pi/btn.pl & > /dev/null 2>&1
volumioの場合は以下
/home/volumio/oled.pl & > /dev/null 2>&1
/home/volumio/btn.pl & > /dev/null 2>&1
保存して閉じる。
CTRL + x を押す
さらに y を押す
そのまま enter を押す
緑色LEDのために以下を
sudo bash -c "echo dtparam=act_led_trigger=heartbeat >> /boot/config.txt"
さらに
sudo reboot
として、再起動後 液晶、ボタンが動けばOK
##################################
シャットダウンについて
本基板いちばん右のボタンがシャットダウンボタン。
シャットダウンできているか判別は、ラズパイの緑色LEDの点滅がとまっているか。
点滅がとまったら、電源スイッチで電源をオフにしてよい。
なので、コネクタは、これよりすこし短めにしておくとよい。
次は表
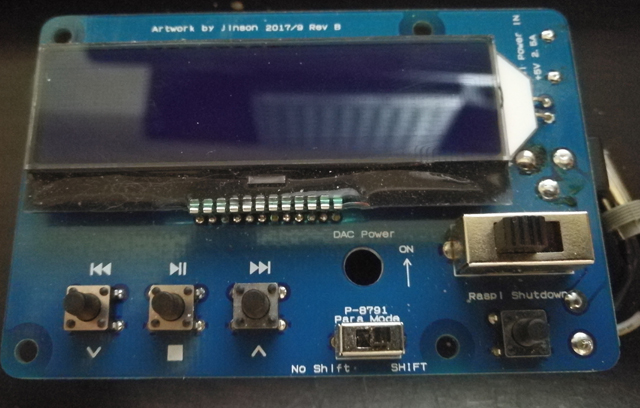
見ての通り実装していくが、液晶について注意。
まず、液晶の両面に保護フィルムが貼ってあるので、両方剥がす。
さらに、バックライトユニットは、発光側に、ツヤあり保護フィルムがはってある。これも剥がすこと。
剥がさないと、高さがましてしまい、スペーサの高さとの兼ね合いもあってよろしくない。
スペーサーだけど、これはシャットダウンスイッチとフレームがぶつかるので、逃げがつくってあるほうにあわせる。
写真とろうとおもったけど、黒くてうまく写らない。
まあ、充ててみればわかる。シャットダウンのタクトスイッチとスペーサの枠が当たるので。
あとは、DACに給電するACプラグをつければOK.
まあ、実際のところ、好きに作ればよし。
★スクリプト導入および設定
既に、ボタンや液晶スクリプトを入れている方は、単純にそれらを上書きする。
導入方法は以下の通りとなります。
Moode4の手順です。
moodeの導入手順はこちら
http://moode.local/
として、ブラウザから操作する。
・Moodeメニュー -> Configure -> System と進む。
スクロールしていくと「OPEN Web SSH terminal」というのが見つかるので、Openをクリック
ユーザ pi
パスワード moodeaudio
でログイン
volumioの場合は、
http://volumio.local/DEV/
にアクセスして、ssh を enableにする。
putty等で接続
解説はmoode向けに書いておあるが、基本おなじ。
ペーストのやり方は右クリック
ホスト名 volumio.local
ユーザ volumio
パスワード volumio
・i2cを有効にする (volumioでは不要)
以下のコマンドを投入していくが、手打ちはシンドイので、ペーストする。
ブラウザで右クリックすると「Paset from browser」というメニューが出るので、
それを選択して、以下のコマンドをペーストしていく。
sudo raspi-config
として、Interfacing Options -> I2C に進む。
これもまあ、画面見ればわかる。
カーソルキーで操作。エンターで確定
I2Cのとこで、とりあえずYESを選びまくり、最後にFINISH
・必要な物を入れる
sudo apt-get update
しばらく待つ。なにかいわれたら Yを返答
sudo apt-get install i2c-tools kakasi
これもおなじくしばらくまつ。基本的にYを返答
・スクリプトを入れる
wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_4para.bin
wget http://www.telnet.jp/~mia/alt_btn.bin
さらに
mv alt_4para.bin lcd.pl
mv alt_btn.bin btn.pl
つづけて
chmod 755 lcd.pl
chmod 755 btn.pl
・自動起動に登録
sudo nano /etc/rc.local
一番最後の行に
exit 0
があるので、その上に以下を追加
/home/pi/lcd.pl & > /dev/null 2>&1
/home/pi/btn.pl & > /dev/null 2>&1
volumioの場合は以下
/home/volumio/oled.pl & > /dev/null 2>&1
/home/volumio/btn.pl & > /dev/null 2>&1
保存して閉じる。
CTRL + x を押す
さらに y を押す
そのまま enter を押す
緑色LEDのために以下を
sudo bash -c "echo dtparam=act_led_trigger=heartbeat >> /boot/config.txt"
さらに
sudo reboot
として、再起動後 液晶、ボタンが動けばOK
##################################
シャットダウンについて
本基板いちばん右のボタンがシャットダウンボタン。
シャットダウンできているか判別は、ラズパイの緑色LEDの点滅がとまっているか。
点滅がとまったら、電源スイッチで電源をオフにしてよい。